続 平安朝 (平安時代) 衣装
|
|
|
| 色出しについて 草木染の権威の諸先生により「延喜式縫殿式 927年成立 ・967年施行 」の染め方法の記述を再現されています。各先生により微妙に色合いが異なります。くれぐれも、アバウトでご覧下さい。 zipangu |
 <位階と服色 差異表示 男性> 差異表示の為の位階と服色の変遷
<位階と服色 差異表示 男性> 差異表示の為の位階と服色の変遷
 ▼一条帝(天皇)の時代 、990年(正暦)〜1011年(寛弘)より以前 養老令 衣服令 延喜式の服色等
▼一条帝(天皇)の時代 、990年(正暦)〜1011年(寛弘)より以前 養老令 衣服令 延喜式の服色等
| 帝(天皇) 黄櫨染 |
一位 深紫 六位 深緑 |
上記の 「色」 は、晴れの日(特別イベント日)(お正月 ・大嘗祭 等々)に着用するロングジャケット(袍)の色です。 |
帝(天皇)のみ着用可のオンリーワンカラー 【黄櫨染】 日本紀略 嵯峨天皇弘仁11年(820年)2月の詔 「朔日受朝大小諸会則用黄櫨染衣云々」 西三條家装束抄 「黄櫨染 (文。桐竹鳳凰) 天子常に召す云々」 帝(天皇)のみ着用可のオンリーワンカラー 【麹塵(きくじん)】 臨時祭 ・観劇(特別イベント)、弓場始等に着用。 |
太上天皇のみ着用可のオンリーワンカラー 【赤色】 西三條家装束抄 「赤色。太上天皇の御袍。赤白の橡(つるばみ、ドングリの事)と称する是れなり云々」 |
親王、孫王、源氏の子孫のみ着用可のオンリーカラー 【黄衣(黄丹)】 西宮抄 「無品親王孫王源氏公卿の子孫等、昇殿を聴りて未だ無位の程、之を着す」 北山抄 「黄衣(文小葵)儲君以下無品親王の袍」 |
★麹塵に関する 「謎」 |
桃華蘂(ずい)葉胡曹抄によると青白橡は、「麹塵、山鳩色に同じ」 「青色の衣、又麹塵と号す」と記されています。 とすると、麹塵 ・青白橡 ・山鳩色 ・青色はすべて同色になります。 胡曹抄は室町時代の中期から後期に活躍した一条兼良が書いた本です。 私どもがお世話になっている 「日本の伝統色」 に対する権威 「山崎氏」「長崎氏」「吉岡氏」「福田氏」の 皆さん見解が異なります。 少なくても嵯峨天皇の820年に 「この色」 が存在していた事は確認できます。 その後1480年成立一条兼良の胡曹抄までの時の流れは660年。 青白橡の染め原料は 「紫草」 と 「刈安」 と 「灰」 (媒染剤) と確定しています。 (延喜式縫殿式により)「紫」と「黄」 で 「黄緑」 を染め出す事になります。 顔料の絵の具で混色したら 「黄緑 」には絶対になりません。 補色同士の色ですので必ず 「グレー」 になります。 吉岡氏は 「日本の色を染める」で、麹塵の色を「室のほのかな明るさで見てみると、薄茶色に見える。 ところが、輝くような太陽の光のもとで見ると、緑が浮き立つように見える。」 と述べています。 |
麹塵色に対する私ども ZIPANGU の見解 |
1 光の分量により、色が変わって見える。 2 麹塵に対して染め原料説明の書物がない。 3 4色を同色とした一条兼良の文献は500年から600年以上に渡る時の隔たりが有る。 以上から、 |
青白橡は、後染め織物 (織り上がった布を染める) であり、 麹塵は、 先染め織物 (糸染めをしてから織り上げて布にする) であると結論づけてみました。 極細い絹糸を糸染め(紫 ・黄染)して緻密(経糸・緯糸の色違い糸)に織り上げた布 (生地) は、 シャンブレー状に仕上がり、光の分量と角度により 「色」 が微妙に変化して見えます。 シルクバーバリのコートが見る角度により、玉虫色に観える現象の感じと考えます。 |
★帝(天皇)⇔黄櫨染 太上天皇⇔赤色 親王、孫王、源氏の子孫⇔黄衣(黄丹) について |
長崎氏は「色 ・彩色の日本史」で「天子 ・皇太子 ・上皇の地位を象徴する色は、 一日の朝 ・昼 ・夕の太陽の色を模したものである。」 と述べています。 |
朝日(若さ)の「黄赤」⇔黄衣(黄丹) 昼日(現役)の黄櫨染? 夕日(お年老り)の「橙」⇔赤色 |
朝な、夕なの感じは何となく・・・ですが、日中の光の黄櫨染 は (色的に)如何なものか思います。 しかしながら、時の流れを 「色」 で表現する発想に 「日本文化の香り」 をお感じになりませんか。 |
☆ その際の服色 「生地(布)」 は、五位以上の方々 冬 表綾で裏平絹 夏 表綾で裏こめ織と云う薄物。 綾は斜めに糸が走っている絹生地 平絹は縦緯に糸が走っている絹生地 こめ織は細い糸で固く織った生地で紬の薄物の感じと想像して下さい。序でに、 |
☆ 羅 ・ 紗 ・絽 の違い |
羅 (うすは ・うすぎぬ・ラ) は、こめ織より薄地で斜文の有る物。 紗 (うすぎぬ ・シャ)は、平織りの状態に生糸を経糸に絡ました (絡み織り) 軽く薄く粗めの絹織物。 絽 (ロ) は、紗と平織りとミックスした絹織物。緯糸の3本、5本おきに透かし目を作った織物。 |
 ▼平安朝(時代)中期、みやびの時、藤原道長さんの時代の服色
▼平安朝(時代)中期、みやびの時、藤原道長さんの時代の服色
| この頃までには、染色技術・技能が以前に比して格段と向上していた風です。 (現代風には、スキルUP。) |
深紫 →濃(紫) 浅紫 →薄(紫) |
奈良朝(時代)、否それ以前より、紫と紅 (染め原料の「紫草の根」と紅花(末摘花)が非常に高価の為) 勢い、 fashionトレンドカラーと云うか 「高貴」 な色に。 皆さん、より 「紫」 色を表現したい結果、官位、一位〜四位まで 「黒橡」 色になったとの事です。 (桃華蘂(ずい)葉胡曹抄 ・装束要領抄に依る) |
一位 深紫 |
草木染師、山崎氏の 「草木染日本色名事典」で 黒橡について 「袍の色の深紫 ・浅紫 ・深緋が色を競って濃く染めたことから、黒色になったが、それでも純黒ではなく紫味がほしかったために五倍子 (ふしの事) で染めることが多かった。」 と記されています。 紫色に拘る凄まじい程の執念を感じませんか。次に、 |
五位 浅緋 |
七位以下は、服制の色に関して廃されたとの事。紫 ・紫 ・紫色のオンパレードです。従いまして、 三位以上と四位との差異表示は、ボトム(袴)とロングシャツ(下襲)の文様の有無と下襲裾の長短になったと。 |
★ 三位と四位の実質差異、 |
上達部 (かんだちめ) の皆さんの三位と参議 (宰相) の四位は帝 (天皇) にダイレクトに、謁見可能。 以外の四位と五位と六位の蔵人 (お側係) は帝のプライベートパレス (清涼殿) に入場可の方々 (殿上人 ・堂上 但し、帝との直接会話は不可で通訳要。) いずれの方にせよ、スーパーエグゼクティブ。 |
清少納言さんのお薦めは、 上達部では宰相(三位)中将 (参議で近衛府の中隊長) 公達 (エリート) では頭中将 (蔵人のヘッドで近衛中隊長) と頭弁 (蔵人のヘッドで行政実務官)。 (近衛府は表面状は内裏警護係のはずが実際のお仕事は 「舞楽」 係。) どの時代 (とき) も、オジサマ方より、セレブでお若い方が良いのかも・・・。 |
★ ボトム (袴) の色 (表袴 ・赤大口袴 ・小口袴) |
衣服令では、表袴(うえのはかま)の色は 「白」 とされていました。但し、裏地は 「紅」、三位以上は文様有り。 赤大口袴は、下袴 (ロングフレアートランクスの感じ) で、表裏地ともに 「紅」。束帯着用時は必ず着用の事。 小口袴は、ロングトランクスの感じで、桃華蘂(ずい)葉胡曹抄では 「濃紅梅」 色と有ります。 |
飽きなく追求した紫味の 「黒」 のジャケット、「白」 のボトム、「掻練襲 ・懐練襲(光沢有り紅)」 のロングシャツ。これに、「黒」 の帽子(冠)と 「黒」 の沓(靴)で平安時代中期(みやびの世)の出で立ちファッションになります。 |
 <女性の服色 ファッションカラー>
<女性の服色 ファッションカラー>
左から、「(中)紫」 「藍」 「縹」 「緑」 「刈安」 「山吹」 「紅」 の7色です。 |
ジャケット(唐衣・細長・小袿・表着)の1月〜12月までのおおよその流れ。 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| インナー(袿)は、各々、個性的な「襲色目」 でコーディネーション。目立つ「補色」か、ご一緒の「匂い」・「薄様」か。『 さあ、どうする、彼女たち 』 ここが「 センス・Sence 」の見せどころ ってな感じ。戦いの火蓋が切られる事に・・・。 |
| ボトム(袴)は、すべての季節、紅・くれない色。 何とかして くれない とデートに遅れちゃう。ガンバ みなさーん。
旧暦 (太陽太陰暦) の1月スタートは、約、今の太陽暦の2月4日の 「立春」 とお考え下さい。 |
 <女性のボトムの袴は紅色 紅袴>
<女性のボトムの袴は紅色 紅袴>
| 女性のボトムの袴は、
晴れ (オフィシャル) も褻 (カジュアル )ともに皆さん (老若)、紅色の袴を着用していたとの事。 但し、平安中期以前は、その限りではなかった感じです。 源氏物語の御幸の巻 「落栗色の袷の袴」 と有ります。 |
この時代以後、若い上臈 (身分の高い女性) やエグゼクティブのお嬢さん・お孫さんは オフィシャルにおいて濃紫色を着用されていた様子です。(桃華蘂(ずい)葉胡曹抄) 又、(女官飾抄) には 「袴は紅のはりばかま。祝の時濃きはり袴夏冬同じ。」 濃きは濃紫色。 二つの文献は室町中期時代のエリート知識人 一条兼良さん。 |
 <禁色(きんじき)と聴(ゆる)し色>
<禁色(きんじき)と聴(ゆる)し色>
| 何時の世も、規制された中でのオシャレの競い合い。派手めの色は、ご年配 ・上司の方々には不好評?
平安の世には、お洒落な女性がいらっしゃいました。 |
新古今和歌集十八雑下に、 「延喜 (901〜923年) の御時、女蔵人内匠(にょくろうどたくみ)、白馬節会(あおうまのせちえ)見侍りける車より、紅の衣を出しければ、検非違使(警察官)糺(ただ)さんとしけるに、女蔵人内匠『大空に照るひの色を禁(いさ)めても天の下には誰れかすむべき。』かく云えりければ、糺さずなりにけり。」 |
女蔵人内匠は、帝のお側係担当のお姉さん。白馬節会は1月7日に行われるイベント。 それをお車 (牛車) で見に行かれた彼女 (紅色のジャケットを着用できない方) が スモークガラス (御簾) 車なので内緒で紅色のジャケットを着て会場に出向く途中、 ついうっかりロングガウンの裾を御簾の外に出し衣。 それを見咎めたお巡りさんに対する彼女の言い回し、 「お日様 (の色の紅色) を禁止なんぞしたもんなら、誰もこの世じゃ生きていけないって云うの」って。 さすが機転が利いてお洒落なお姉さんじゃございませんか。 お巡りさんも洒落がきく、オシャレな方でございます事。 |
禁色の制は、桓武帝(天皇)の延暦二年(783年)、清和天皇貞観十二年(870年)等、 この時までに幾度か発せられますが、延喜式(927年成立・967年施行)以後は、 このページのTOPで紹介した 帝(天皇)・太上天皇・親王等の着用ロングジャケットカラー、及び、「紫色」 が禁色。 紫色は三位 (上達部) 以上は着用可能カラー。 |
「禁色」は、 ・麹塵に似た青(緑)色 ・赤色に似た深緋と深蘇芳色 ・黄衣(黄丹)に似た梔子(支子)色 ・紫色。 とは云うものの、余りのギスギスはいかでかで、お許しが有れば、その限りに有らず。 |
それが 「聴(許)し色」。 清少納言さんのお薦め、頭中将など、六位の蔵人 (若きエリート達) のジャケットカラー、青(緑)色は聴し色。 赤 ・青 (緑) ・黄・ 紫色を禁止されたら女性は ドーすんの。 そこは云わずもがなのコンコンチキ。 スーパーエグゼの殿方は、ス・テ・キな女性には甘ゆ〜いのが世の常。 |
紫式部日記に 「御簾の中を見わたせば、色ゆるされたる人々は、例の青色・赤色の唐衣、地摺の裳、表着は蘇芳の織物なり。」 ってな感じで、めでたく?、殿方、お気に入りの皆さんは 「許される?」 事に相成りました次第です。 |
 <平安時代の生地(織物)の種類>
<平安時代の生地(織物)の種類>
| 織物 緯 (よこ・ぬき) 糸で文様を出したもの。
綾文 経 (たて) 糸、緯糸ともに練絹で地文織り上げしてから染めた絹。 練緯(ねりぬき) 二重織物 地文の綾の上に別糸で別文様を織りだしたもの。 |
 <御堂関白記 具注暦 曜日の順序>
<御堂関白記 具注暦 曜日の順序>
| 現存する最古の日記、藤原道長さんの御堂関白記(998〜1021年)は具注暦に書かれた 「備忘録」 でした。
今の世の、日付・曜日が有る手帳にメモ書きの感じでお書きになっていたみたいです。 週休二日制でない平安の世。お休みはどの様になっていたのでしょうか。 具注暦は陰陽寮で作成された暦で、日付(干支)・七曜日・月齢などが漢字で記入されていて余白があったとの事。 そこに、藤原道長さんは誰々さんと会ったとか、誰々ちゃんと逢ったとか記していたのでしょうか? 日付によりイベント日が決められいた平安時代と云う事ですので、それ以外の日は 「お休み」? 七曜日が記されていましたので、土・日はあったのでしょうが、お休みであったかどうかは定かでありません。 |
| ★ 七曜日の順序の決められた経緯(いきさつ) ★ |
昔、昔の天動説 (地球が中心) では地球から遠い惑星順は、 土星→木星→火星→太陽(日)→金星→水星→月。 1時間毎に7つの星に時空間が支配されてると考えていました。(バビロニア人占星術 ・ギリシャのカシウス理論。) |
ある日の一日 深夜0時をスタートとして、一時間毎に7星を順番に配していくと、 |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1日 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 |
| 2日 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 |
| 3日 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 |
| 4日 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 |
| 5日 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 | 木 | 火 | 日 | 金 | 水 | 月 | 土 |
| 同様に、6日は 木 、7日は 金 になります。これが、土→日→月→火→水→木→金 の順番。
これで一週間の出来上がり。 |
土曜日からのスタートだったのが、キリスト教、安息日の発想で日曜日がスタートに。 コペルニクス・ガリレオ・ニュートンと来て地動説が証明されたにも関わらず、七曜日の順番は変更なし。 この固定概念は不動なのかしらん。 |
この日本は、明治5年(1872)12月3日=明治6年(1873)1月1日から「太陽暦」(新暦)を開始。 具注暦はそれまでは使用されていました。 (これのみでは有りません。) さて、お休み日はどうだったのと気になる皆様、何と日曜日がお休みになるのは、その3年後からなのです。 太政官布告に依りますと、明治9年(1876)4月より (対象はお役人さん達) 日曜日がお休み、土曜日はお昼まで。 こんな感じですので、藤原道長さんは具注暦はお持ちでしたが、日曜日は必ず休日では有りませんでした。 |
現時点で確認されている惑星の地球から近い順序は、 (太陽と月を含むと 2006年現在) 月→金星→火星→水星→太陽→木星→土星 (ここ迄は紀元前に肉眼で発見済み)以後は望遠鏡により、 →天王星(1781)→海王星(1846)→冥王星(1930)→第10惑星?(2003) となります。 * 2006年8月24日に冥王星と第10惑星?は惑星から除外されました。 |
 <五節会 ・五節句(供) 陰陽五行説>
<五節会 ・五節句(供) 陰陽五行説>
| 日曜休日の実施時期の3年間のブランク。即、実行できなかったのは、お休みが少なくなってしまうからでした。
それ迄のお休みは、1日、6日、11日、16日、21日、26日の月6回。 太陽太陰暦は約354日の12ヶ月と約3年に一度の調整の約384日の12ヶ月+閏月。 年で約150〜160日の休日。 その中の五節句。 正月七日(人日) ・三月三日(上巳) ・五月五日(端午) ・七月七日(七夕) ・九月九日(重陽)。 |
平安の世は、五節会。元日 ・白馬(あおうま1/7) ・踏歌(3/3) ・端午(5/5) ・豊明(とよのあかり) +五節の舞。 五節会からは除かれていますが。七夕 ・重陽の節会も当然ありました。 七夕は、私どもに大いに関わります。 たなばたは棚機女 (たなばたつめ) で機織り姫の事です。 織り姫と彦星。 ベガ(織女星 ・赤い星)に裁縫 ・書が上手になる様に女性はお願い事をしたそうです。 |
ここで、「五節会」。 この 「五」 が五行説。 木 ・火 ・土 ・金 ・水。 陰陽は、月 ・(太陽)日。 中国古来の宇宙観。 ここに七曜の一週間が完成する事に。 |
『月と太陽という二つの星を陰陽として、他の五つの星を五行の星として陰陽五行説にとりこむと、 二と五の和もちょうど七となるので、古代中国ではまさしく天啓として受けいれられたにちがいない。』 |
中国では数字が重なる事を忌み嫌った感じですが、この日本では逆手に取り、お祝い事に。 更に鶏 ・卵ですが、ちょうどそれらの日が、季節の変わり目のお日柄となり、衣替えの契機に。 イベント日に向けての 「お洒落」 の競い合い、宴の後のファッション・アイテムの変更。 これぞ、四季折々のfashion感性。いとうつくし。 |
(暦に纏わる件は、「暦と日本人」 内田正男氏 並びに 「歴史と占いの科学」 永田久氏 を参考にしています。) |
 <みやびな世の平安時代は、ファッショナブルの極み>
<みやびな世の平安時代は、ファッショナブルの極み>
| みやびな平安の世であった 「京の都の小宇宙」。 ( 藤原道長さんの時空間 )
一月九日からの 「除目」 (人事異動)と権力闘争を除けば、とっても平安・安寧の時を刻んだと思われる空間。 「節会」 と云うイベント並びに饗応と贈答 (送り手・受け手両者ともに)。 「賀茂祭」 と云う過去の忌まわしい出来事に対する鎮魂に名を借りた饗応と贈答。 「新嘗祭」 と云う収穫に対する感謝の気持ちを表しての饗応と贈答。 心赴くままの自然界へのお祝い・感謝としての喜びのお酒 桃咲け(酒)・桜咲け(酒)・菊咲け(酒) と お食事。 儀式と云う 「お仕事」 と 「お遊び」 とをすべてフュージョンした(小遊びの権力闘争も渾然とした) 時空間。 こんな 「大人?の感じの世界」 で、華やいだ 女性 ・男性 ファッション。 <極上の 「気持ち」 の生産 ・消費のし合い 。> 「貨幣」 と云う 「交換財」 と 「流通」 と云う 「物の怪」 には牛耳られてはいませんでしたよね っと。 |
 <平安貴族のパーティ(饗宴)のお食事とは>
<平安貴族のパーティ(饗宴)のお食事とは>
| ファッションと切っても切り離せないお食事は、一体どうだったのでしょう。 平安時代の食事事情は?
どの様な食事をされていたか推察可能な書物は 「類聚雑要抄」 になります。とても具体的に記されています。 類聚雑要抄の記載内容に永久3年 (1115年) 7月21日 戊子(つちのえね)と有り、それ以降の物となります。 |
★お正月の饗宴(御歯固 (おんはがため))のお料理 |
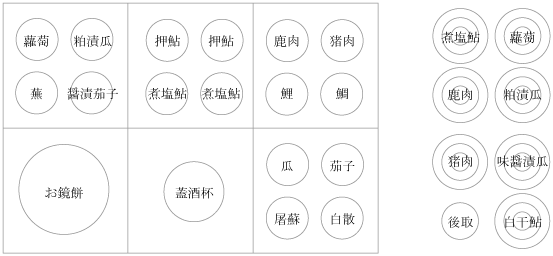 |
後取(しんどり)は 「宮中で、元日より三日間、天皇に屠蘇(とそ)・白散などを供する時、お余りをいただく役。 白散(びゃくさん)は「正月、酒に入れて飲む屠蘇の一種。 蘿萄 (らどう) 又 (ろうごう) とも読むみたいで、どうも大根の様です。 |
お肉料理 猪肉、鹿肉、無い場合は、猪肉は雉に 鹿肉は水鳥?に。 お魚料理 鯛、鯉、白干鮎、押鮎、煮塩鮎 野菜など お漬け物 粕漬瓜、味醤漬瓜、醤漬茄子 お飲み物 屠蘇、白散 お供え物 |
お正月イベント料理で、たぶんお屠蘇 (お酒) が主になり「おつまみ」程度の献立になっているのかも。 原文は京都大学電子図書館 「類聚雑要抄 1」 でご覧頂けますので、見比べて下さい。 |
★引っ越し祝いパーティのお料理 (旧暦7月21日) |
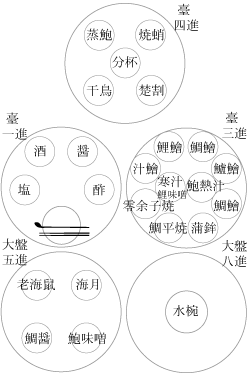 |
|
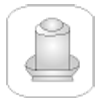 |  |  | 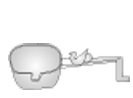 |
| 二進 これ不明 | 六進 酒□? | 九進 水 | 七進 酒 |
| 干鳥、零余子を除けば、海 ・川の幸、海鮮料理、海の珍味、お魚さんのオンパレード。 とても豪華なお料理。
高級料亭も思わずびっくり仰天って感じがしませんか? お肉類少々で健康にも気づかっている様子。 調味料も揃っています。スプーン (匙・さじ) も有ったのですね。銀製デザインスプーン 「類聚雑要抄 3」 の数々。 尚、この引っ越し祝いパーティは、関白右大臣殿、東三条殿移御の饗宴の模様となっています。 ここでやや疑問が。1115年の関白は藤原忠実になり、既に1112年に確か太政大臣に就任していた筈ですが? 貴重な記録を残して下さった方が正確かも? 美味しいものを前にして細かい事は・・・・・。 |
★ 平安時代の清少納言 ・紫式部の方々 (女房・キャリア) の女性の素敵な 「心模様」 (文化) は、 ★ |
☆ 「平安時代のキャリアウーマン」 で詳しく展開していますので、一度ご覧下さい。 ☆ |
| ★ リ ン ク 先 ★ |
  |
| Maccafushigi |
| Copyright © 2006〜 ZIPANGU Co.,Ltd. All rights reserved. |