戦国時代 空白の衣装時空 京都
|
|
 <全く服どころではない戦国時代>
<全く服どころではない戦国時代>
| 服の歴史、この戦国時代はお休みです。
甲冑、兜と云う、コンバット (戦闘) ファッションは置いてきます。 ここでは、日本文化の中心であった京都地区の戦国時代歴史模様を整理して、 やがて来る、解き放たれた消費時代、安土 ・桃山時代までを埋めてみたいと考えます。 |
歴史の教科書に於いて、概ね、戦国時代は、1493年4月の 「明応の政変」 からとしています。 細川政元が足利10代将軍、足利義材 (義尹 ・義稙) に叛旗を翻し、堀越公方の足利政知の息子、 足利義澄を11代将軍として担いだ時からになります。(1489年にも画策) 細川政元 (1466〜1507) は、応仁 ・文明の乱に於ける東軍のリーダー細川勝元の息子。室町幕府の管領。 足利義材 (在職1490〜1493・1508〜1521)(1466〜1523) は、8代将軍義政の弟、義視(1439〜1491)の息子。 堀越 (伊豆国) 公方の足利政知 (1435〜1491) は、6代くじ引き将軍足利義教の息子。 足利義澄(在職1494〜1508)(1480〜1511)は、足利義政の養子に。 とっても、分かりにくいので足利家の、無味乾燥で味気ない系図を示してみます。 |
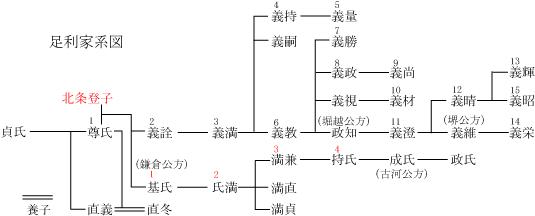 |
*上の系図の将軍出発点である、足利尊氏と北条登子さんとは関係は、「女性史の流れでは」 を確認下さい。 *数字の黒 は征夷大将軍順で、数字の赤 は鎌倉将軍 (鎌倉公方) 順になります。 |
*古河公方 (こがくぼう) 1455年に鎌倉から下総国 古河に引っ越してから自称。現在の茨城県古河市。 *堀越公方 1457年鎌倉公方として鎌倉に向かうも辿り着けず、伊豆国堀越 (韮山) に留まった呼称。 現在の静岡県伊豆の国市。1493年明応の政変関連で伊勢新九郎盛時 (後の北条早雲) により断絶。 |
8代将軍足利義政 (在職1449〜1473)(1436〜1490) と日野富子 (1440〜1496) は連れ合い (ご夫婦)。 お二人にお子さんができなかったので義政の弟で義政の養子になった足利義視 (1439〜1491)。 義視の奥さんは、日野富子の妹さん。このお二人のお子さんが足利義材になります。 義視が義政の後を継ぎ、9代将軍になる段取りが、思いがけず、義政と日野富子の間にお子さん誕生。 そのお子さんが、足利義尚(よしひさ) (在職1473〜1489)(1465〜1489) が応仁 ・文明の乱を経て、9代将軍に。 義尚の家庭教師は、一条兼良が担当。ここ迄のお話しは、皆さんよくご存じの筈です。 しかし、この後日本史の教科書は室町文化挿入でいきなり桶狭間の織田信長になってしまい70年間は何処かへ。 応仁 ・文明の乱の東軍の主将は、細川勝元 (1430〜1473)、龍安寺で有名なお方で、足利義視のシンパシー。 一方、西軍の主将は、山名宗全 (1404〜1473)、西陣(時間軸逆)にお住まいで、日野富子と義尚 のシンパシー。 1473年に細川勝元と山名宗全は仲良くお亡くなりになり、彼らの息子さん達がやがて和睦へ。 8代将軍義政は、銀閣寺造営に勤しみ、煩わしい政治向きには無頓着? 日野富子さんは、目出度く息子、義尚が足利9代将軍の座に納まり、万々歳。 足利義尚が1489年、近江国、六角高頼 (1462〜1520)(近江佐々木源氏) との諍い鎮圧出陣中に病死。 後継者を巡り、いつもの世の出来事に。結果的には、政元アンチ派の足利義材 (よしき) が10代将軍に。 しかし、1493年、明応の政変で実質日本国家運営は、一応、管領の細川政元の手に委ねられる結果になります。 |
 <戦国時代 京都の実質支配者の変遷>
<戦国時代 京都の実質支配者の変遷>
| 時 代 | 天 皇 | リーダー | 傀儡将軍 | 管 領 | 事 件 |
| 1493年04月 | 後土御門天皇 | 細川政元 | 足利義澄 | 細川政元 | 明応の政変 |
| 1500年10月 | 後柏原天皇 | 細川政元 | 足利義澄 | 細川政元 | 後柏原帝践祚 |
| 1508年04月 | 後柏原天皇 | 大内義興 | 足利義稙 | 細川高国 | 義興1518年帰郷 |
| 1521年12月 | 後柏原天皇 | 細川高国 | 足利義晴 | 細川高国 | |
| 1526年04月 | 後奈良天皇 | 細川高国 | 足利義晴 | 細川高国 | 後奈良帝践祚 |
| 1527年03月 | 後奈良天皇 | 三好元長 ・細川晴元 | 義晴と堺公方義維 | 高国と晴元 | 義晴 ・高国は近江へ |
| 1529年08月 | 後奈良天皇 | x | (足利義晴) | 高国と晴元 | 三好元長は阿波へ |
| 1534年09月 | 後奈良天皇 | (六角定頼) | 足利義晴 | 細川晴元 | 義晴京都へ帰る |
| 1536年09月 | 後奈良天皇 | 六角定頼 ・細川晴元 | 足利義晴 | 細川晴元 | 晴元京都へ帰る |
| 1546年11月 | 後奈良天皇 | (六角定頼 ・義賢父子) | 足利義輝 | 晴元、六角定頼 | |
| 1549年06月 | 後奈良天皇 | 三好長慶 | (足利義輝) | (細川氏綱) | 義輝と晴元は近江へ |
| 1552年01月 | 後奈良天皇 | 三好長慶 | 足利義輝 | 細川氏綱 | 義輝京都へ帰る |
| 1553年08月 | 後奈良天皇 | 三好長慶 | (足利義輝) | 細川氏綱 | 義輝は近江へ |
| 1557年10月 | 正親町天皇 | 三好長慶 | (足利義輝) | 細川氏綱 | 正親町帝践祚 |
| 1558年12月 | 正親町天皇 | 三好長慶 | 足利義輝 | 細川氏綱 | 義輝京都へ帰る |
| 1564年07月 | 正親町天皇 | (足利義輝) | 足利義輝 | x | 三好長慶が死去 |
| 1565年05月 | 正親町天皇 | (三好三人衆 ・松永久秀) | 候補 足利義栄 | x | 足利義輝が自刃 |
| 1568年02月 | 正親町天皇 | (三好三人衆 ・三好義継) | 足利義栄 | x | 足利義栄に将軍宣下 |
| 1568年09月 | 正親町天皇 | (織田信長) | 足利義昭 | x | 信長 ・義昭が京都に |
| 1573年07月 | 正親町天皇 | 織田信長 | x | x | 室町幕府の滅亡 |
| *管領の欄、細川晴元以降は管領職補任の事実は確認不可、実質で。(「日本史辞典」 角川書店 )
*大内義興(おき) (1477〜1528) 周防 ・長門 ・豊前 ・筑前 ・安芸 ・石見国守護、上洛後山城国守護、管領代 *細川政元は実子が無く、3人の養子を迎える。 細川澄之 (1489〜1507) 実父は関白 九条政基 (1445〜1516) 細川澄元 (1496〜1520) 実父は阿波国守護 細川義春 阿波国守護 細川高国 (1484〜1531) 実父は摂津分郡守護の細川政国の子、政春 摂津 ・丹波 ・讃岐 ・土佐国守護 最終的には細川 ・右京大夫家(京兆家 京兆は 「左京職・右京職」 の唐名)の家督は高国が継ぐ事に *細川晴元 (1514〜1563) 父は澄元 阿波国守護 *細川氏綱 (1514〜1563) 細川高国の養子 実父は摂津分郡守護 細川尹賢 最後の京兆家に *三好元長 (1501〜1532) 細川晴元の家臣 三好は今の徳島県三好市 *三好政長 (1508〜1549) 三好一族ながら三好元長とは、折り合いが合わなかった人物 *三好長慶 (1522〜1564) 元長の嫡男 晴元との不和で父を亡くした長慶は1539年僅かな手勢で遺領を奪還 晴元は六角定頼に頼み、長慶と和睦、しかし1548年長慶は晴元に叛旗を翻し敵対 *三好義継 (1551〜1573) 長慶の養子で三好家の継嗣 実父は長慶の弟、十河一存(そごうかずまさ)(1532〜1561) *松永久秀 (1510〜1577) 三好長慶の家臣 *六角定頼 (1495〜1552) 六角高頼の次男で家督を継ぐ 近江半国守護観音寺城主(滋賀県蒲生郡安土町) 楽市令を出し信長の楽市楽座の元となる、今は楽○? *六角義賢 (1521〜1598) 六角定頼の息子 彼の姉さんが細川晴元に嫁いでいるので晴元は義理の兄さん *足利義維 (つな) (1509〜1573) 堺公方 ・平島公方 足利義材 (義尹 ・義稙) の養子になる *足利義晴 (在職1521〜1546)(1511〜1550) 母は日野富子の姪 *足利義輝 (在職1546〜1565)(1536〜1565) 母は近衛尚通のお嬢さん 奥様は近衛前久 (1536〜1612) の妹 *足利義栄 (在職1568〜1568)(1538〜1568) 母は大内義隆 (1507〜1551) のお嬢さん *足利義昭 (在職1568〜1573)(1537〜1597) 母は近衛尚通 (1472〜1544) のお嬢さん |
 <三十六計逃げるに如 ( し) かずの戦国時代>
<三十六計逃げるに如 ( し) かずの戦国時代>
| 1493年
細川政元は、前10代将軍足利義材を京都から追放します。義材側からは、京から逃げ出す事になります。 義材は、最初は越中富山の万金丹ではなく、越中国、畠山尚慶(尚順)(1475〜1522) の所に身を寄せます。 1498年には越前国(一乗谷 現在の福井県福井市城戸ノ内町)、朝倉貞景 (1473〜1512) の所へ。 1499年に京の都を目指すますが、六角高頼に阻まれ、一路、周防国へ。そこには西国の雄、大内義興が。 一方、京都では、細川政元が修験道に入れ込み、幕府の仕事に支障を来し、1507年6月に養子の澄之により、 あの世に旅立ちます。7月には父を死に追いやった澄之は、同じく政元の養子の高国との戦闘により討ち死に。 *修験道は、「役小角(えんのおぬず・おづの)を祖と仰ぐ日本仏教で、日本古来の山岳信仰に基づき、山中の修行 による呪力の獲得を目的・・・。」 と広辞苑に記されていますがこの方面は全くの門外漢です。 |
1508年 京の混乱に乗じて、大内義興と足利義材及びサポート九州 ・中国地区軍団 (出雲国守護代、尼子経久 (1495〜 1541) 等) らは、日本の当時の首都である京都に向け1508年の正月に出発します。 この情報を得ていた京都地区軍団、傀儡将軍の足利義澄、執政で細川政元の養子の澄元らは策を巡らせますが 塩梅が悪く、おまけに同じく政元の養子の高国とは仲違いになり、高国は3月に伊賀国に逃亡、 4月に入り、政元は近江国甲賀へ、足利義澄は近江国近江八幡に逃げ出してしまう始末。 有力武将 (コマンダー )は京を去り、京の都に残されたのは、後柏原天皇だけと云う状況になりました。 今谷明氏の 「戦国大名と天皇」 に依りますと、後柏原天皇はとても困窮されたとの事です。 彼は、大内義興に対して、「治罰綸旨 (ちばつりんじ)」 を発給しており、義興を朝敵にしていたからです。 機を見るに敏だったのか、義興と内通していたかは不明ですが、 細川高国はもぬけの殻の京都に帰ります。4月末に和泉国の堺港に着いていた義興軍団に対して、 高国は堺に出向き、義興 ・足利義材に取り入ります。義興の裁断で高国は細川家の家督をゲットする事に。 足利義材 (この時の名前は義尹) は、7月に再度征夷大将軍に復帰し、大内義興は山城国 (京都) の守護に。 大内義興は、足利義材が将軍職に戻ったので、帰国しようと考えている矢先、 後柏原天皇が宸翰 (しんかん 帝直筆の書) を出し、彼の下国を阻止しようとします。 帝と義興との交渉役がこの時代の服の資料でお世話になった 「三条西実隆」 さんです。 大内義興が折れたのか、三条西実隆の説得工作が功を奏したのか判りませんが、 義興はこの年から、1518年までの11年間、京都に留まります。 彼の在京により、京都地区の治安が保たれた事になります。故に、この時のリーダーは大内義興。 義興が京に滞在中、彼息子の大内義隆 (1507〜1551)、重臣の陶興房 (1475〜1539) らが領国を固めていまし たが、先に帰国した尼子経久により、領国事情が不安定になり、1518年に義興は帰国します。 当然、京都地区は、政局 ・治安が悪化する事態に。 1519年に地元の阿波で燻っていた細川澄元は蜂起します。1520年3月に細川高国らは敗れ入京されます。 しかしながら、同年5月に細川高国らは京を奪還し、澄元は阿波に引き返します。 ここでの問題は、足利義材 (この時の名前は義稙) と細川澄元がつるんでいた事でした。 |
1521年 「室町時代の衣装」 の 「応仁の乱後のお金 ・社会事情」 で触れました様に、 後柏原天皇は1500年に践祚後、幕府財政が窮乏などの理由で、この年まで 「即位式」 が執行されていません。 興福寺の尋尊 (じんそん) (1430〜1508) (父は一条兼良) の伝える所に依りますと、 帝の即位式について、時の管領、細川政元は下記の様に語ったそうです。 |
「朝廷におかれても、即位の大礼の御儀など無益である。 |
更に帝をサポートする筈の公家の皆さんまでも、この意見に頷(うなず)いたとの事です。 「権威と儀式」 で生活しているお公家さんがこれでは、ご自分達の存在を否定している事になります。 権威は 「厳 (おごそ) かな儀式」 有っての物種。 これでは、庶民が何にも御利益 (ごりやく) がなく、お賽銭もないからお正月の初詣をパスするのと同じ? 権威や御利益は 「心のなせる問題」、経済的利得だけでは計れない事案の筈です。 ここの処が 「日本文化」 のさせる業 (わざ) のひとつと考えるのですが、如何お思いですか? H/K これは最近の若者の 「話は変わって」 の略との事。 話を本題に戻します。 その即位式がやっとの金策を以て、ようやく1521年の3月20日に挙行と決定していました。 それにも関わらず、何と細川高国との不和が続いていた足利義材 (義稙) は、 なんとまあ、イベント日の前に、すたこら京都を逃げ出して大切な儀式に参列しなかったのです。 この様な体たらくですので、細川高国はこの年の末にお子さんのいなかった足利義材 (義稙)に見切りを付け、 11代将軍義澄の次男、足利義晴を12代将軍に擁立します。 (義澄の長男は足利義材 (義稙)の養子になっていた為、義晴に。) 暫しの間、平穏の日々でしたが、 1526年4月に後柏原天皇が亡くなり、後奈良天皇が践祚、 践祚式やらお葬式が執り行われ、やっと儀式が終了し 「ほっ」 としようとした最中、 8月に細川高国の身内同士のいざこざが勃発します。高国の処置が悪かった感じで、彼は窮地に追い込まれます。 この機に乗じ、1508年に高国に追い落とさらた細川澄元の遺児、晴元は反高国で動きます。 |
1527年 細川晴元はこの年、未だ、14歳(数え)で、実質は彼の家臣、三好元長の貢献が大。 晴元軍団は、傀儡将軍に時の将軍、足利義晴の兄の足利義維を擁していました。 この年の2月に阿波から晴元軍団の三好元長らが京都に迫り、桂川の合戦で勝ちを収めると、 足利義晴及び細川高国は近江へ逃亡。足利義維は上洛せず堺に留まった為、堺公方と。 |
 <組織の危うさ、崩壊模様>
<組織の危うさ、崩壊模様>
| 2人で 「組織」 が出来上がり、3人集結で組織に必ず、「セクト (派閥)・チーム」 が生じます。
この組織を法律用語?では 「法人」 と呼んでいます。 *ここでは、「法人」 を 「個人」 と別ける意味合いで使用しています。 法律上の権利義務が生じる主体、資格などの 「法人」 とお考えにならないで下さい。 人が集結した形が組織=法人です。 1人ですと、ご自分の意思で一応、行くも、退くも、迂回するも対処 ・決定可能です。 組織=法人ですと意思決定の仕方で、 |
独裁・・・組織リーダーの意思で対処 ・決定 合議・・・組織内の方々の意思を無理矢理まとめて決定 |
独裁であろうが合議であろうが、相手 (個人、組織=法人) に意思伝達をする事が必要になります。 この意思伝達をする方 (その意思の責務を負う方) がリーダーと云う事に。 故に、リーダーは、その組織体の代表者 ・トップ ・ボス ・親父? ・お袋です。 組織は、知り合いお友達同士、家族、町内会、会社(利潤を生み出す法人)、以外の法人、国家 等々になります。 |
「意思決定」 の際の一番の基本は、皆さん 「もの心」 がつき始めた頃からうすうす感じ、 齢 (よわい) を重ねる毎にクッキリしてくる 「お金」 になります。早い話は、「利得計算」 です。 若者言葉の 「どっちがお得」 「お得じゃん」 と云う代物です。 私達日本人は、と云うより、昔の日本人はと云っても良いのかも知れませんが、 この事柄を、奥床しくも?はっきり口にする事を 「否」 としてきました。 しかしながら、江戸時代の後期に南蛮人?(ドイツ人)の方が、臆面もなく?さらりと表明されました。 |
「下部構造は上部構造を規定する。」 (カール・○クス) |
かと云いましても、記している私ども ZIPANGU は彼の信奉者では有りませんのでご心配なく。 彼の日本の歴史観にはいささか苦言を呈したいと思っています。 只、彼の凄い所は、ホントに 「言い切った事」 です。この事には、後ろから小さな音で拍手をしたい気持ちです。 |
組織の基本は 「イジメ」 です。 なぜなら、ご自分達の組織にアンチを唱える個人 ・組織に対しては、 「泣き寝入り」 「長い物に巻かれる」 「敵前逃亡」 の対処策を立てず、果敢に挑む事にした場合は、 「イジメ」 の方法論で対処せざるを得ないからです。 「イジメ」 を貫徹する際のツールで物を云うのが、 「お金」 と 「武力」 と 「甘くて辛辣な囁 (ささや) き」 (些細な演出詞)。 |
これらの具体的事例が、この戦国時代の日本で垣間見られます。 決して 「イジメ」 を礼讃 (らいさん) している訳ではありません。現実を見つめ、イジメの対処策として・・・・・。 それでは、たくさん固有名詞が出没して面倒くさいかも知れませんが、少しばかりお付き合い下さい。 |
 <管領職 細川家の攻防 戦国時代>
<管領職 細川家の攻防 戦国時代>
| 1508年以降の守護国 (⇒は実子 →は養子)
細川本家=京兆家の経済的基盤の分国は、摂津 ・丹波 ・讃岐 ・土佐国 と 山城国 (1518年以降) 細川分家 (庶家) は、備中 ・和泉 ・阿波 ・淡路国 |
阿波国守護 阿波国守護 摂津分郡守護 政国の子、政春⇒細川高国 (京兆家へ) 摂津分郡守護 政国の子、政賢⇒細川尹賢 (摂津分郡守護) ⇒細川氏綱 (京兆家へ) 和泉半国守護 元有の子、元常→細川藤孝 (幽斎)(1534〜1610) (後の肥後熊本藩主) |
1521年の時点で12代将軍になった足利義晴は細川高国の金銭 ・軍事力あっての賜物でした。 |
|
⇔ |
|
| 1526年 |
1527年 |
1527年 |
1527年 |
1528年 |
1528年12月 柳本賢治が京都駐留の三好元長軍と戦、敗走して河内へ。 |
1529年 |
1529年 |
1530年 |
1530年 |
1531年 |
1531年 |
この約4年間の京都は、1528年に六角定頼が細川晴元軍団との和睦交渉を行い、 一時、足利義晴は京に滞在しますが、足利足利義維 との和族不成立に伴い、即、近江に引き返すします。 この交渉で、停戦派の三好元長 ⇔ 主戦派の柳本賢治 ・三好政長 ・細川高国とに分裂。 1527年2月に京都を制圧した三好元長は、1529年8月に細川高国との折り合いが悪くなり阿波に帰ります。 どんな感じで、三好元長と細川高国が仲直りしたのか不明ですが、約2年弱京都はリーダー不在?。 京都を緩衝地帯として、堺と近江の睨み合いが続いていた事になります。 しかし、忘れてならないのは、「後奈良天皇」 が、京都に佇まっておられました。 |
 <戦国時代の地でいくバンドワゴン効果と日和見>
<戦国時代の地でいくバンドワゴン効果と日和見>
| 「勝ち馬に乗れ」 のバンドワゴン効果と 「日和見」 を鮮やかにもこの歴史が私達にお示し下さっています。
細川高国軍団 v.s. 細川晴元軍団の戦 (いくさ) の成り行き。 細川高国軍団は、桂川の合戦で敗退し、一時京都を去ります。 しかしながら、細川晴元は傀儡将軍候補、足利義維を擁して京の都に足を運びません。 京を占拠していたのは、三好元長軍事担当リーダーです。 細川晴元は、足利義維の官職を得ようと朝廷権力に手を回し足利義晴の座を追い落とそうとの魂胆。 実質リーダーがこの体たらくでは、未だ 「我、関せず」 (ご自分の所で精一杯かも)で、状況を見守っている 回りの皆さんは、頭目が誰になりそうかの 「小田原評定」 です。 劣勢の細川高国ですが、未だ管領?諸国巡りで、シンパシー(味方、同調者)を得る作業をします。 しかしながら、賛同者は浦上村宗とやや日和見の六角定頼 ・やや動きの朝倉教景を除き、 全く動こうとはしませんでした。 軍事力に秀でた三好元長のお陰で、細川晴元は一応、勝利したと云っても過言ではありません。 |
*バンドワゴン効果とは米の経済学者、ハーヴェイ・ライベンシュタイン (1922〜1993) が 1950年に発表した論文(Bandwagon, Snob and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand)。 経済学では、社会的消費量が多い程、個人も多くを購入しようと云う意欲が高まる効果としています。 これって、「隣の美代ちゃんが持ってるから私も欲しい。」 って感じ。 皆さん一度は???。 |
 <一向宗(浄土真宗)と法華宗(日蓮宗)>
<一向宗(浄土真宗)と法華宗(日蓮宗)>
| なぜか、人心が荒廃した時と、人心が高揚し過ぎた時にファッション (流行) となる宗教。
鎮護国家のツールとして出発した日本仏教。(宗教関係のお仕事に携わっておられる方には失礼します。) やがて、藤原道長さんの時代には、極楽浄土に往生できると云う幻想として、 公家政権から武家政権に変容する時代頃からは 1 政府権力の精神的?支え、及び、中国外交貿易事務官として。 2 世の中の末端を支える方々が唯一心の拠り所、安堵感として。 天台 ・真言密教を除き、浄土宗、浄土真宗、日蓮宗、禅宗などは、平安時代後期から鎌倉時代に出現しました。 禅宗は鎌倉幕府 ・室町幕府の庇護の下、別の動きをしますが、 それ以外の宗派は、概ね、富も権力も名誉も持ち合わせない方々に支持されていたと云う事になっています。 富も権力も名誉も持ち合わせない方々を以後 「民 (たみ)」 と表現します。 この戦国時代になりますと、民を基盤としていた浄土真宗、日蓮宗は民を圧倒的に組織していました。 それらの民を束ねる、宗派のリーダー達は既に官僚化された組織体になっていて、 (どんな組織に於いても、組織構成員の肥大化に伴い、組織運営上どうしても官僚化せざるを得ません。) 宗教組織は非生産 (物を生産して販売する組織ではない) 幻想組織ですので、 宗派のリーダー達の経済的基盤は、民から僅かばかりの 「お布施」 になります。 ところが、ギッチョン、「塵も積もれば山となる」 で、組織の方々が増大している訳ですから、 莫大な経済的基盤を保持する事になります。 宗派のリーダー達は 「富」 を背景として、宗派の厳かな?理念を横に置き、 時の権力者に対して、脅したり、すかしたり、迎合したりして、ご自分達の組織の利得を追求します。 特に、応仁 ・文明の乱 以後、日本分国国家組織体の大部分が疲弊してしまいます。 特に、京を含む畿内地区、各分国で京の煽りを受け、東軍 ・西軍の各セクト・チームに分かれた代理戦争地域。 細川氏を含め、三管領四職で京都に生活シーンを持つ守護大名分国。 各分国で守護、守護代として民と密着し、力強い軍事力を背景に持ち、 民を含めた利得の考察ができ得なかった地域リーダーを擁してしまった分国。 それらの分国の民にマッチッグしたのが浄土真宗、後の一向宗と命名された軍団 (組織体) でした。 |
| 1531年 |
1532年 |
この時、一向宗 (浄土真宗) のトップリーダーは、 本願寺門主10世 証如光教(しょうにょみつのり) (1516〜1554)。父は円如、祖父9世 実如の後を継ぐ(1525年)。 |
1532年 |
1532年 |
1532年 |
山科本願寺は焼失しますが、一向宗 (浄土真宗) 徒は健在です。故に諍 (いさか) いは継続し続ける事に。 山城国の中心、京都町衆が属する 法華一揆軍団 ⇔ 一向一揆軍団 京の周辺に生計を営む農業従事者の構造。 法華一揆軍団を利用する細川晴元政権。一進一退の攻防戦が続く日々。 |
1533年 |
土地境界争い、税金徴収獲得先確保等の極めて日常の決済を仰がなくてはならない方々にとっては、ある時は 芥川に、又ある時は、傀儡将軍足利義晴のいる近江、六角定頼の観音寺城近くの桑実寺にと足を運ぶ煩わしさ。 |
1534年 |
一方、泰然自若な?朝廷組織はこの間、高みの見物。後奈良天皇は、ご自分の即位式の挙行実現を計り奔走。 践祚後、費用が集まらず執り行なわれなかった即位式。 その費用を賄ったのが、分国での諸事情で 「天皇の権威」 を必要とした 「戦国大名」。 即位式費用の80%方を請け負ったのが、大内義隆 (1507〜1551)、先年京都に在住した大内義興の息子です。 彼以外は、朝倉孝景(10代) (1493〜1548) 長尾為景 (1471〜1542?) 土岐頼芸 (1502〜1582)。 見返り、ご褒美は、大内義隆→太宰大弐 長尾為景→暗黙の了解 土岐頼芸→美濃守。 |
1536年 |
1536年 |
*生憎、「松本問答」 の内容は不明です。高尚な宇宙的な命題だったのでしょうか?ご存じの方はご一報下さい。 |
| (参考文献 「日本史辞典」 角川書店 「戦国時代の貴族」「戦国大名と天皇」 今谷明 ) |
▼ この戦国時代ページの分量が多くなりましたので頁を変更します。 ▼ |
NEXT 「続 戦国時代 空白の衣装時空 京都」 へ |
| ★ リ ン ク 先 ★ |
  |
| Maccafushigi |
| Copyright © 2006〜 ZIPANGU Co.,Ltd. All rights reserved. |