�\��P�@����
|
|
|
 ���\��P�@���� �E�\�� �E�ň� �E�܈� �E�P �E�ց�
���\��P�@���� �E�\�� �E�ň� �E�܈� �E�P �E�ց�
| �P�̏���݂��ꖇ�ꖇ�d�˂Ă������ɂȂ�A�Ō�ɏ� �E���߂�Z���A�w���Ў�ŁA�\��P�̊����ł��B |
���@�t�ėp�@�� |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| �\��P �w�� | �\�� | �ň� | �l�� | ��� | ��� | �P |
| �@�� �u�\��P �w��v �� �y�h�o�`�m�f�t �̃t�����g�y�[�W�ł��B
�@�� �u�t�ā@�\�� �E�ň� �E�P�̊g��G�v �Ŋe�X�̑傫�ȊG�����������܂��B |
���@�H�~�p�@�� |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| �\��P �w�� | �\�� | �l�� | �O�� | ��� | ��� | �P |
| �@�� �u�H�~�@�\�� �E�ň� �E�P�̊g��G�v �Ŋe�X�̑傫�ȊG�����������܂��B
�@�� �����Ԃɗ]�T�̂��L��̕��́A�u�݂�� �\��P �������㒆�� �T�C�g�}�b�v�v �������������B |
 ���t�ďH�~�̏\��P��
���t�ďH�~�̏\��P��
| �t�̏\��P | �Ă̏\��P | �H�̏\��P | �~�̏\��P |
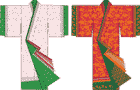 |
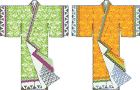 |
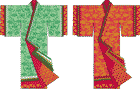 |
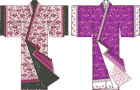 |
| ���@�d | �R�@�� | �ҁ@�� | �ԁ@�k | ���@�e | �g���݂� | ��̉��g�~ | �������₤ |
| �t���� | �t�g��G | �Đ��� | �Ċg��G | �H���� | �H�g��G | �~���� | �~�g��G |
| ���@�u�g��G�v�ŁA���́u�F�̔z�F�v�̖��������g�̖ڂŊm�F�������B��
���@�l�G�܁X�̎��R�̈ڂ�ς��ŕ\�����镽�����̏����B�B�� |
| �� �\��P�͒ʏ��B��������ɂ͏\��P�̌ď̂͂Ȃ��A�e�X�P�i���ŕ����Ă�ł��܂����B
�� �\��P�̒P�i���ƒ��p�����́A�u������ �i��������j �ߑ��v �ł��������܂��B |
���\��P�ƕ����ɏo�Ă���̂͊��q����������B�@�@�i���͋���j |
�@���������L�@���l�\�O�@�@���q����ȍ~�ɐ����B �@�@�u�퐶�̖��̎��Ȃ�A���d�˂��\��P�̈߂��߂��ꂽ��E�E�E�B�v �@�@���̏V�[���͌����@���q���d�m�Y�ŊC�ւ̔�э��ݏ�ʁB�R�����Ȃ̂ɂS���ėp�̈ߑ��Ƃ́B �@�@����萼���ɏo������ہA���V�[�Y�����������ɂȂ����̂��B�����ׂ̈������͐���t�@�b�V�������B |
�@�����@���O�@�@�����N�ԁi1368-1375�j���̐����H�@�@�����V�c�i�݈� 1287-1298�j(1265-1317) �@�@�u�����V�c�̒��{�̌䑕�ЂɁA�g�~���\��P��߂ɁA�����F�̌�ЂƂցA�g�̑ł�����A�G���̏�� �@�@�@�������̌䏬�݁A�ԎR���̌䓂�߁A����́i���E�A�����j�����̌�ցE�E�E�B�v �@���̌�̐��ŁA���������i�����j���܂߂��P�Q�i�܈߁j�P�i�ŏ\��P�Ɖ]���悤�ɂȂ�B�ݎO���ł��\��P�ƁB |
�@���d�˂̐F�� �u�܉؉@�a�������v �ł͏ォ�率 �E���� �E���� �E�� �E�� �E�g�̃R�[�f�B�l�[�g�B�i�P�F�ځj �@�g�~�̐F�͓������g�~ �E�g�~ �E���g �E�g �E�g �E�g �E�łV���ɂȂ�̂͊����~�̕�������B���d�͉ĕ��B |
�@�ԎR���͏d�i�����ˁj�F�ڂŕ\�����F�ŗ����G�K�F�B�u�d�C�@�����}���ʎj�v�̒��҂֖̊ڐ������H���A �@�F�ڂ́A����40�N�ɂ���l�̂����߂ɂ��q���i����Ăāj�ɏ������߂����̂Ȃ̂ŎQ�l�ɂ��ĂƂ̎��B |
�@���A�\��P�̏d�v�A�C�e�����݂͗��\����B�P�i�ЂƂ��j�������ɉ]���ƈꖇ�z�łȂ��܂�Ԃ��z�L��B �@��̂W���̊G�̉E���Ɍ�����ΐ����͗l�����̕����B���������i�����j�݂̂��{���̒P�߁i�ЂƂ��j�B |
 �������[���l�p�@�\��P��
�������[���l�p�@�\��P��
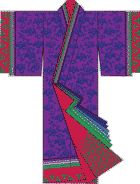 |
|
 ���\��P�ɂ��Ă̏��X��
���\��P�ɂ��Ă̏��X��
 �� �z�i�f�ށj�E�F�i�J���[�j�E�`�i�V���G�b�g�j
�� �z�i�f�ށj�E�F�i�J���[�j�E�`�i�V���G�b�g�j
| ���C���[�h���b�N�i�d�˒��t�@�b�V�����j�̋ɂ݂̏\��P�B�@�@�d���ɂ��Ă� �u�\��P�i�d���E�����j�v �ցB
�A���A�\��P�𒅗p�ł����̂́A�������������t���L�����A�[�ȏ�̕��X�Ɍ����܂��̂ł����ӂ��B |
�z�i�f�ށj�́A�S�āA�ɏ�� �u���v ���g�p���Ă��܂����B�ŋɏ�̕z�͂��ג����i���j����̃C���|�[�g�f�ށB �@�����E�⎅����̎h�J���{���ꂽ�z�@�R���i���R�E�ɐ�������\�j�ȂLj�؍������Ă��Ȃ������̌��z�B �@�����i�������j�@�����i�˂肬�ʁj�i���z�����_�炩���d�グ����H��̕z�j�@���i�������́j�ƌĂꂽ �@�����W�E�т̕z�@�D��ŕ��l��\���������X�̕��z�X�@���蕨�Ɖ]����v�����g���L�����͗l�B |
�F�́A���̎���Ɣ䂵�đ��F���Ȃ��ƍl�����܂��B �@�Ɖ]�����A�ނ��낱�݂̂�т̐��̕���������������B���p�x�[�X�ōl����Ƃł��B �@���݂̃u�e�B�b�N�̓��ŕ���ł���m���̐F�����͂��q�l�L���b�`�C���O�p�ɐ������L��̂�����H�B �@������́A���E�C���^�[�J���[����ŁA�Q�N��̃g�����h�J���[�������ƌ��肵�܂��̂� �@�t�ɐF�i����������A�F�������Ȃ��Ȃ�_�B �@�X�ɁA���̎���i�Ƃ��j�́A���F�p�̌������L�x�łȂ����̂ł�����A������ �i�g�j ����߂�ɂ��Ă��A �@���̎��X�̋�Ԗ͗l �i�C���E���E�ޗ��E���ߎt����̃X�L�����X�j �ɂ��A �@�قȂ�� �i�g�j ���o�����鎖�ɂȂ镪�A�����I�ɐF���������Ȃ�܂��B �@���A���F�ɂ����Ė�������i���w�����̓����j���́A��ɐA���������ɂ��Ă��܂����B�ʏ́u���ؐ��߁v�ł��B �@����Ɋւ��܂��ẮA���t�ŕ\���s�\�ł��̂ŁA�ʓr���B�W���A���ŕ�����l�ɂ��܂��B �@���݂̂�т̐��̓��o�� �u�F���v �ł��B�݂�т̎���Ԃł������܂�Ȃ��Ǝv���鉽�Ƃ��f�G�ȕ\���B �@ �u�F���v �� �u�Ԗ��v �ŕ\�����Ă����̂ł��B���̎��́A�u���W�� �����i�Ԗ����F���Ɂj�v�Ŋm�F�������B �@�t�ďH�~�̏\��P�̗l�ɁA�G�ߖ��Ɋe�X�����Ȃ��A �@�X�ɁA�������������Ȃ̂́A�G�ߒ��ɂ����̌o�߂�\�����Ă��܂��B |
�@���ɏP�F�� �i�����݂̕z�F�̃J���[�o���G�[�V�����̑��́j �̎��̗�����L���Ă݂܂��B |
| �@�t�́A | ���� | �� | ���d | �� | ���� | �� | ���� | �� | ���U�P | �� | �U�P | �� | �R�� |
| �@�H�́A | �e�d | �� | ���e | �� | ����Ћe | �� | ���g�t | �� | �g���݂� | �� | �����g�t | �� | �U�g�t |
| �@���� �i���j ���̈ꌾ�B�@�e�P�F�ڂŁA���̎��X�̎��R���i��͂����A�����ȐF�ω��\�������Ă��܂��B
�@�݈ꒅ �i�́j ���ɐF�Â������A�������d�˒����A�� �E������ �E�O���S �E���Ȃǂ���S�F������d���āA �@�g�[�^���g�[�� �i�e�F�̒��a�����F���̑S�i�j �����̎���ƃ}�b�`���O����S�z�� �E�S���� �E�S�͗l�ł��B �@�u�P�F�ڂƏd�F�ڂ̈Ⴂ�v �́A�ʂɋL���܂��B |
�`�́A�G�ŕ�����Ǝv���܂��B���ǂ��ł������ɒ��Ă�����̂�������l�ɍ쐬����Ă���̂����X�ł��B |
 |
|
| ������́A�ގq�i�������j�Ɖ]�������߁B�ʂ����đ��������H�A���A�q�ׂ̌`�͕s���B�@�e�B�A�����E�o���b�^���H
���A�w��ƒ����ɂ��ẮA������� �u���W�� �\��P�i�w��E�����j�v �ŐG��Ă��܂��̂ł����������B |
 �� �\��P�̏d���̕s�v�c��
�� �\��P�̏d���̕s�v�c��
| �����ŁA���[ �i�L�����A�̏����j �̃W���P�b�g �i��ԏ�ɒ��p�j �� �u���߁v�A
�P����W���P�b�g�̒��������ɂP�Q���i�э��݁j�Ƃ��܂��B �P�ȊO�͕\�E���̂P���ł��̂ŁA�P���ɂP���̂P�P.�T�{�����d�ʂɂȂ�܂��B ���d�ʂ����悻�P�O�s�Ɖ]���Ă��܂��̂ŁA�P���������W�V�Og�B ���̐��ł́A�����̕��ł�����J�V�~�A�̃����O�R�[�g�Ŗ�P�s�A�j���̃g�����`�E�_�X�^�[�R�[�g�Ŗ�X�O�O���B �̂ɁA�����̐��̏����B�͂��̃R�[�g���P�O���d�˒����Ă������ɂȂ�܂��B �f�ނ͖� �E�ȂłȂ� �u���v �ł��B �m���ɗI�v�̎��Ԃ��߂�����Ă�����ł�����A�����̊ɖ����͑S�R��肪�L��܂���B �����[���������q�ŏ\��P�̂܂܃t���[�����O�̏�ŕ��������������ʼn��ɂȂ��Ă��� �ƗL��܂��̂� �u���z�c�v ����ɂ͏d���̂�������܂���B �����������ō�������肪�����܂��B �\��P�� �u�f�G���v �̍ŏd�v�� �u�P�F�ځv �͕\���\�ɂȂ�̂ł����A �ꒅ�������X�O�O���̌����n �i�\ �E���j �̌��݂��l����� �u�d�F�ځv ���\���ł��Ȃ��Ȃ�܂��B ������A�\�����悤�Ǝv���A �ꒅ�̕\�n���ɔ��������n�ŗ��n�� �u�F�v ����ɓ��߂����Ȃ���Ȃ�܂���B �v�͕\�n���������n�ŗ��n���������n�̈ꒅ�ƌ������ɁB �u�P�F�ڂƏd�F�ڂ̐F���{�v �͂�����B |
���@���i�V���N�j�̕z�̏d���A�u�� �i����߁j�v �̏ڂ������͂�����ł����������B |
 �� �\��P���݁i�������j�Ɠ��� �E���݂̐��n�̌���
�� �\��P���݁i�������j�Ɠ��� �E���݂̐��n�̌���
| �\��P�ɂ��āA�ǂ̕������J���Ă��A
���n�̌��݁i���j�Ɋւ��ĐG��Ă�����̂�����������������܂���B ��{�I�ɂ͒P�������������݂ł��镗�ȏ����������Ă���̂��w�ǂł��B �������̗l�ł��Ə\��P�̏d���̕s�v�c���ŋL���܂����ʂ�A �d�F�ڂ̈ꒅ���\�n���ɔ����ė��n���n���Ȃ̂łƂĂ��ϋv�������� �i���C�W���������j �i���ɂȂ�܂��B �����璴�o�u���[�ȓ����������� �i�Ƃ��j �Ƃ��Ă��A �G�ߖ��Ɏ���� �i�v���[���g�����j �����̐��ʂ����߂��Ă�����ł����璅���͌��肳��鎖�ɁB �m�F�\�ȏ\��P�̑S�̑���`������ԌÂ� �u�G�v �́A�u��������G���v �ł��B �����̏������� �i���������́j ������ƁA��ԏ�ɒ��p����Ă���W���P�b�g �i���߁E���݁A�����͕\���j �� �C���i�[ �i�܈߁j �Ȃǂɔ䂵�Č����������܂��B �ꒅ�̏d������X�O�O���Ƃ��Č� �i�V���N�j ���n�̕\���Q���d�˂̌��݂͂����悻�O.�W�o����P.�Q�o�ʂł��B �@�i�\�n���n�Ԃ̋�C���ʊ܂ށB�j ������P���ɂV���`�W���A���p���Ă����ƍl����͔̂@���Ȃ��̂��ƍl���܂��B �������A�݂̌��� �i�C���i�[�j �Ɠ��߁E���݁A�����͕\�� �i�A�E�^�[�W���P�b�g�j �̌��݂��قȂ�A �W���P�b�g�p�̈ꒅ�� �u�d�F�ڂ̈ꒅ�v �i�\�n���ɔ����ė��n���n���j �ɂȂ鎖���\�ł��B �܂��Ă�A�W���P�b�g�ɂ͍��ȕ��l���{���ꂻ�̕����݂������鎖�ɂȂ�܂��B �������ӂ݁A���̐��̏��� fashion �Ɠ������A �A�E�^�[�͌����C���i�[�͔������̂ŃR�[�f�B�l�[�g���Ă����̂łȂ����ƍl����̂ł����E�E�E�E�E�B ���@�V�����ł��܂�����A���A���m�点���܂��B�@�@�������m�F�ł��Ȃ��̂��ƂĂ��c�O�ł��B |
 �� �d���ƌ��݂̖��������ق����u���Ίہv
�� �d���ƌ��݂̖��������ق����u���Ίہv
| ��́A�\��P�̏d���ƌ��݂̖��_������������@�B
����́A���z�ɂ��錦�����ׂ���Ή������܂��B �\���͂��o�� �u���v �̑���������Ȃ��ׂ��E��v�ŁE����L��E���Ȃ₩�E���F���Ղ�����Ηǂ��̂ł��B ���̂��\���A�����݂����q�q�c�@������ĂɂȂ��Ă��� �u���Ίہv�B ���Ԃ�A���̉�ȕ�������̂��\����� �u���Ίہv ���ŗL�����̂ł͂Ȃ����Ǝ��ǂ��͍l���Ă��܂��B ��������ɓ���A�����A�B�Y���Ƃ̈�̒��ɂȂ��� �u���� �E���D�� �E�����i�v�B �����͏��Ίۂ�����Ɏ��炳��Ă����悤�ł����A�₪�āA �����������s��̌o�ύ��������ѓO����A���̌o�߂ɏ]��������������������\�����炳�ꂽ�����ł��B ������ �E���G �E���������A�u�o�ύ������v �̓���I���������ɁB ���ŏЉ�Ă��܂��A ��z�{�q�q���� �i�d�����ȏ\��P�j �Ɣ��q�q�c�@�A���c���q���� �i�y�������̏\��P�j ������ׂĉ������B �{�e�[�ƃT���[���Ⴂ�܂��ł��傤�B�����̐��̓T���[�ŗL�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �u���Ίہv ���̌����ŗL��A�C���[�W������⓮���Ղ��A�u�d�F�ځv ��肪�e�ՂɂȂ�܂��B |
 �� �\��P�͒P�i�P�Q���i�́j�łȂ����������L�q
�� �\��P�͒P�i�P�Q���i�́j�łȂ����������L�q
| �h�ԕ����\�l�@������@���i�a�勿�� |
�w���� �i�c�@���́j ���[�Ȃ�ǂ��́A���A���A�R���A�g�~�A�G���̂��F���A �@�Ƃ肩�͂��A��l�ɎO�F�Â������ւ�Ȃ�B �@�ЂƂ�͈ꂢ����܂A�O���뒅����́A�\�܂ÂA����͘Z�������A �@����������͏\���A��\�ɂĂ��L�肯��B�x |
���̖����̑����ɓ������������������A���A�㓌��@�i�������q�j�Ȃǂ́A |
�u�����Ȃ鐰��̎��ɂ����[�̏d�˘Z��߂���܂܁A �@���̑��i�̂�j�����͂���ɁA���̔��i�a�̍c�@���A�@�j��ɂ��͂��܂��ƁA�ނÂ���ꂵ�v |
�Ƃ������ɂ���܂��B�@�@�\��P�̖��� �E�d���� �u�\��P�i�d�˒��j�v �������������B |
���A�\��P�̒P�i�����́A���������A���q����ł́A�삵�������ɕω����Ă��܂��B �@�@ ������́A�u���f�B�[�X�̏\��P�̕ϑJ�v �����m�F�������B�@�r�b�N�����Ă��܂��܂���I�I |
 �� �������̂��D�݂̐F�H
�� �������̂��D�݂̐F�H
| �������� �u��������@��顁v �ɂ����āA
����������āA���蕨�ŗ~���� �i�����A�ޏ����D���������j �f�G�� �u���̐F�v ���������Ă��܂��B |
�u�g�~�́A���ƁA����������������ɁA�������̌䏬�݁A���l�F�̂����ꂽ��́A �@���̌䗿�A������̍ג��ɁA��₩�Ȃ�~���Ƃ�Y���āA�ЂߌN�̌䗿�Ȃ߂�B �@�����|�̊C���̕��A�D�肴�܂Ȃ܂߂�����ǁA���Ђ₩�Ȃ�ʂɁA �@���ƔZ���~����ẮA�Ă̌䂩���B �@������Ȃ��Ԃ��A�R���̉Ԃ̍ג��́A �@���́A���̑ɂ��Ă܂ꋋ�ӂ��A���ւ́A���ʂ₤�ɂāA���ڂ����͂��B �@�����@�@���̖��E�Ԃ̌䗿�ɁA���̐D���ɁA�悵���铂���𗐂�D�肽����A �@���ƁA�Ȃ܂߂�����A�l�m�ꂸ�A�قق��܂ꋋ�ӁB �@�~�̐}�A���A���A��т����ЁA���߂����锒�������ɁA �@�Z�i���j�����A��₩�Ȃ��āA���̌䂩���ɁB �@�����Ђ�肯���������A���ւ́A�߂��܂������ӁB �@���̓�N�ɁA�݂́A���ƐS��������݂������āA �@�䗿�ɂ��鞉�q�̌�߁A���F�Ȃ�Y���āB �@���Ȃ����A�݂Ȓ����ӂׂ��A������������߂��炵���ӁB �@���ɁA�ɂ�������݂� �̌�S�Ȃ肯��B�v�@�@�@�@�@�@�@�@�i�� �i���ʁj �z��j |
| ���i�t�j�̎��̏� | ������ | ���l�F | ���� | �n���� | �n���l�͂Q��ޗL��܂��B �����͕z�����яo�Ă��长 �ŕ��͕z�̒��ɒ��ݍ���ł��长 ���݂̓W���K�[�h�D�@�ŐD��܂��B �C�����͊C�ݕ��i����ۉ������� �������̓t�[�e���̓Ђ��C�~�� ���l���� �u���s�H�|���������g���v �@�@�l�̂������T�C�g�Ŋm�F�������B | ||
| ���̕P�N | ������ | �~�� | �@ | �@ | |||
| ��i�āj�̉ԎU�� | �����| | �Z�~�� | �C�� | �g���� | |||
| ���i�H�j�̋�� | �� | �R�� | �@ | �@ | |||
| ���E�� | �� | ������ | ���� | �@ | �@ | ||
| �k�i�~�j�̖��� | �� | �Z�i���j | ���� | ������ | |||
| ���̓�N | �� | ���q | ���F |
| �������̈����������ւ̃v���[���g �i���蕨�j �́A�������ɒ��ė~�����v���̈ߑ� �i���j �ł��B
�������̊e�X�̏����ւ̎v�����ꕪ�ʂ͂��Ă����A �u�F�v ����ɍl���܂��ƁA�ɂ킩�ɕs���R���������܂��B ���ɂ������ �u���F�v ���ŏ㋉�ō��M�� �u�F�v �Ƃ��Ă��������ɂ����āA ���̏�Ɩ�����l�́A���̈ߑ� �i���j �ł��B ���A�ԎU���́A�\�� �i�A�E�^�[�j�A�����|���� �i�C���i�[�j�A�Z�~���ł��̂ŁA �\���̓��ߗ���50���̕z�ŏ��߂Ď��ɂȂ�܂��B �X�ɁA�u���E�ԁv �͖��d�ł��̂œ~����t�J���[�ňꉞ���L��܂���B �������A�\�������������~�߂ɂȂ����H���������A ����Ȃ��G�ߊ����ɂȂ������Z���u���e�B�[�Ȏ��������A ����⊴���R�����Ǝv���܂���̂ŕs�v�c�Ȃ̂ł����A ���̕P�N�ɂ́A�Q���p�J���[�̍��d�̐F�ɁA ��顂ɂ́A�Q��������R���p�J���[�̎R���ɂ��Ă��܂��B ���̎����́A����l���q���������Ă���̂��A�͂��܂��E�E�E�E�E�B |
 �� �����[�������D���ȐF
�� �����[�������D���ȐF
| �����[������́A���ɂ��A�u���v ���D���� �u�����q�v �ŋL���Ă��܂��B�@���ɂ́A
�߂ł������̂� �u�Ԃ������������ׂāA�Ȃɂ��Ȃɂ��A�ނ炳���Ȃ���̂͂߂ł�����������B�v �ƌ���Ă��܂��B |
| �Z�� | ���� | �� | �j�[ | ���� | �� | �� | �� | 俍� | �� | ���� | �g�~ | �K�N | ���� | ���d | ���� | �e�d | �ɔ� |
| ���A�����[�����S�Ƃ��߂������A�u�~���P �E�����P�̉��P�̐F�ځv �͂�����Ŋm�F�������B |
�u�����q�v �Ő����[�����L���Ă��镽���ߑ��̐F�����̃J���[�W�J�͉��L�ł��������܂��B |
�u�i�i�ɏt�{�ɂ܂��苋�ӂقǂ̎��Ȃǂ̒i�v �͂�����ŁA �u�֔��a�A�\���̂قǂɖ@���@�̐ϑP���Ƃ��ӌ䓰�ɂĂ̒i�v �͂�����ł����������B |
���@���A�����݂�т̐F���T���v�����O���܂����B�u���{�̐F�i�`���F�j���{�v �ł����������B �i�y�h�o�`�m�f�t�j |
 �� ���q����̏\��P
�� ���q����̏\��P
| ���q����̏\��P�͂ǂ̗l�ŗL�������́A�u�\��P�̕ϑJ�v �ł����������B
�u�����v �ɋL����Ă��� �u�݂Ə̂���܈߁v �̒��� �i�\��P�̖����j �ɂ́A�v�킸�r�b�N���E�E�E�E�E�B |
���̎���̐V�����o���� ���[���� �i���d�����j �̓� �u�g�сv �̒��p�`�����Ȃ��Ȃ�܂����B�A������ �i���ʃC�x���g���j �������B �ڂ������́A�u�� �i����E���i�j�͎��f�H�@�����i��܂��j�v �ł��m�F�������B |
 �� �吳�E���a����̏\��P
�� �吳�E���a����̏\��P
| ���@�吳�V�c�̉��l�̒喾�c�@�̂��߂��ɂȂ�ꂽ �u�݁v�B �@�i�喾�c�@�Ɖ�z�{�q�q����́A�o���ł��B�j
���@���a�V�c�̑��ʑ��̍ۂɁA��z�{�q�q�����߂��ɂȂ�ꂽ �u�\��P�v�B ��L�� �u�����w������������ ��Ȓ����i ���{�v �Ŋm�F�ł��܂��B ���� �u�f�[�^�[�x�[�X������v ���啪�ނ� �u�ߕ��v�A�����ނ� �u���Ƒ����v ���Z���N�g���������s�ŁB |
�\���A�ň߁A�܈߂̋ݕ����Ƀ^�b�N�������{���Ă��܂��B��������ɂ͂��̗l�ȏ������L�����̂ł��傤���H �܈߂̐����T���i�́j�̕��ʊ��Ƌ����݂̕��ʂɈ�a�����o���܂��H�@�@�@���ǂ��A���ݒ������ł��B |
 �� ��������̏\��P
�� ��������̏\��P
| ���@���݂̓V�c�̑��ʑ��B�@�V�c�̑��тƔ��q�q�c�@�� �u�\��P �i���q�q�l�j�v�{�����z�[���y�[�W�B
���@���q���e���A�����c��a�_�a�ɉy����̋V ���u�\��P �i�I�{�l�j�v�i�{����HP�摜�폜����܂����B�j ���@����19�N�i2007�N�j 2���ɖ^���D���������ŏ\��P��������������Ƃ̎��ł��B �@�@ �ǂ�Ȋ����Ȃ̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B�h�J���́A���ƁA�� �i�䂩��j �� �u���������v �@�@ �ƂĂ��A�ޏ��Ƀ}�b�` �imatch�j �����f�G�ȃR�[�f�B�l�[�g�ɂȂ�Ǝv���܂��B |
���@2��17�� �i�y�j ���c�_�Ђ�����l�ɐ苒����A�����Ȍ������̌�A�Гa�ɂ��o�܂��� �@�@ �\��P�Ƒ��т�w�̃J�����ڐ���ʂ��Ĕq�����܂����B �@�@ �u�ƂĂ��A�J�b�R�C�[�v ���p �E�`�ł����B �@�@ ���c�_�Ђ̎�F�Гa��w�i�Ƃ����ۂ́A���т��ڗ����A�g�F�̏\��P �i���߁j �͓������Ă܂������A �@�@ ��x �i�ЂƂ��сj�A�Y�[���A�b�v�������_�ł̊G�́A���ɋt�]����\���B �@�@ �Ƃǂ̂܂�́A�\��P���ڗ����A�ߑ��̓_�ł́A���ł����������錋�ʂɗ��������܂��B �@�@ ���̌��ۂ́A�L�j�ȗ��̗B�� �u�ς��Ȃ����v �ɑ�����܂���B���}���́A���߂łƂ��������܂����B ���@����26�N�i2014�N�j10/2 �T�q�����A�����c��a�_�a�ɉy����̋V�� �u�\��P �i�T�q�����j�v�{�����B |
♥�@ ���A�\��P�Ɋւ���V��o����A���̓s�x���|�[�g���܂��B�@���y���݂ɁA����ł́E�E�E�E�E�B |
| ���@�@�@�� �� �N ���@�@�@�� |
 �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ |
| �l���������������������� |
| Copyright © 2006�` ZIPANGU Co.,Ltd. All rights reserved. |